ホーム > ユーザーインタビュー > 勝田 俊輔


ホーム > ユーザーインタビュー > 勝田 俊輔
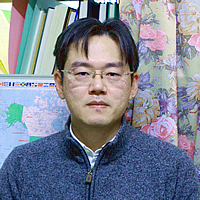
東京大学大学院人文社会系研究科 教授
 今日は、東京大学大学院人文社会系研究科の勝田俊輔先生に 『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』歴史アーカイブ についてインタビューさせていただきます。まず、このインタビューの主旨について簡単にご説明します。弊社Galeは英『タイムズ』、『サンデー・タイムズ』、『タイムズ・リテラリー・サプルメント』、『リスナー』、『デイリー・メール』など、イギリスの新聞、雑誌のデータベースを多数ご提供しています。これらの新聞・雑誌は、専門の研究者以外には内容についてほとんど知られていません。そのような詳しくない人(図書館員や学生の方々)が読んでも面白いと思える読み物を提供し、それを糸口にしてデータベースに興味を持っていただくこと-これがインタビューの主旨です。その点をお含みおきいただき、できるだけ平易にお話いただければ幸いです。今回は『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(以下ILN)がテーマですが、様々な角度からお話しいただき、多くの人がこのインタビューを読みILNの素晴らしさを理解する機会になれば、と思います。それでは、ILNに入る前に、先生のご研究をご紹介いただけますか。
今日は、東京大学大学院人文社会系研究科の勝田俊輔先生に 『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』歴史アーカイブ についてインタビューさせていただきます。まず、このインタビューの主旨について簡単にご説明します。弊社Galeは英『タイムズ』、『サンデー・タイムズ』、『タイムズ・リテラリー・サプルメント』、『リスナー』、『デイリー・メール』など、イギリスの新聞、雑誌のデータベースを多数ご提供しています。これらの新聞・雑誌は、専門の研究者以外には内容についてほとんど知られていません。そのような詳しくない人(図書館員や学生の方々)が読んでも面白いと思える読み物を提供し、それを糸口にしてデータベースに興味を持っていただくこと-これがインタビューの主旨です。その点をお含みおきいただき、できるだけ平易にお話いただければ幸いです。今回は『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(以下ILN)がテーマですが、様々な角度からお話しいただき、多くの人がこのインタビューを読みILNの素晴らしさを理解する機会になれば、と思います。それでは、ILNに入る前に、先生のご研究をご紹介いただけますか。
 専門はアイルランド近代史です。アイルランドの中でも農村社会が最初の研究テーマでした。その後、都市ダブリンの歴史やブリテン世界の歴史にも研究領域を広げています。ブリテン世界というのは馴染みのない言葉かも知れませんが、英語圏と言いかえても結構です。グレート・ブリテンに加えて、独立前のアイルランドやアメリカ、さらにカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどは、かなり似通った政治構造と社会構造を持っていました。そこに注目することで、これまでに見えてこなかったことを明らかにしようとするのが、ブリテン世界の歴史を研究する際の基本的な考え方です。
専門はアイルランド近代史です。アイルランドの中でも農村社会が最初の研究テーマでした。その後、都市ダブリンの歴史やブリテン世界の歴史にも研究領域を広げています。ブリテン世界というのは馴染みのない言葉かも知れませんが、英語圏と言いかえても結構です。グレート・ブリテンに加えて、独立前のアイルランドやアメリカ、さらにカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどは、かなり似通った政治構造と社会構造を持っていました。そこに注目することで、これまでに見えてこなかったことを明らかにしようとするのが、ブリテン世界の歴史を研究する際の基本的な考え方です。

19世紀イギリス史を勉強する過程で「アイルランド問題」に出くわし、アイルランドについて考えるようになりました
 アイルランドを研究対象にお選びになった理由は何ですか。
アイルランドを研究対象にお選びになった理由は何ですか。
 最初はイギリス(グレートブリテン)に関心があったのですが、19世紀のイギリス史を勉強すると、必ず「アイルランド問題(Irish Question)」に出くわします。19世紀を通じて、アイルランドは連合王国の一部でした。アイルランド問題と言うのは一つではなく、貧困、宗教、ナショナリズムなど、19世紀を通じて様々な内容で登場するのですが、どれもが難題でした。こうしたアイルランド問題の存在を知ったことをきっかけに、アイルランドとは何だったのか、と考えるようになったわけです。
最初はイギリス(グレートブリテン)に関心があったのですが、19世紀のイギリス史を勉強すると、必ず「アイルランド問題(Irish Question)」に出くわします。19世紀を通じて、アイルランドは連合王国の一部でした。アイルランド問題と言うのは一つではなく、貧困、宗教、ナショナリズムなど、19世紀を通じて様々な内容で登場するのですが、どれもが難題でした。こうしたアイルランド問題の存在を知ったことをきっかけに、アイルランドとは何だったのか、と考えるようになったわけです。
 近代イギリス史研究の中で19世紀のアイルランドはこれまで注目されてきたのでしょうか。
近代イギリス史研究の中で19世紀のアイルランドはこれまで注目されてきたのでしょうか。
 日本での話に限定させていただきますが、注目されてきたとは言えません。21世紀に入って随分改善されましたが、アイルランドについては依然としてあまり知られていないのが現状です。イギリス近代史の研究者の一般的な認識は、アイルランドというやっかいな地域があり、当時のイギリス人はその扱いに手を焼いていた、というものではないでしょうか。かつては、先進国としてのイギリスを追求することが日本にとって意味があるのであり、アイルランドすなわちイギリスが抱える負の側面を探求することに大した意味はない、との考え方もあったようです。また、あまりにも複雑で重大な問題が潜んでいるので、アイルランドに手を出すのは避けたいという心理も働いていたのかも知れません。
日本での話に限定させていただきますが、注目されてきたとは言えません。21世紀に入って随分改善されましたが、アイルランドについては依然としてあまり知られていないのが現状です。イギリス近代史の研究者の一般的な認識は、アイルランドというやっかいな地域があり、当時のイギリス人はその扱いに手を焼いていた、というものではないでしょうか。かつては、先進国としてのイギリスを追求することが日本にとって意味があるのであり、アイルランドすなわちイギリスが抱える負の側面を探求することに大した意味はない、との考え方もあったようです。また、あまりにも複雑で重大な問題が潜んでいるので、アイルランドに手を出すのは避けたいという心理も働いていたのかも知れません。
 これまでのご研究の中で、ILN(冊子もしくはデータベース)を研究資料としてお使いになったことはありますか。
これまでのご研究の中で、ILN(冊子もしくはデータベース)を研究資料としてお使いになったことはありますか。
 アイルランド農村社会の歴史を調べるときに使いました。19世紀半ばにアイルランド大飢饉が起こります。いわゆる「じゃがいも飢饉」です。ILNはこの飢饉を比較的詳細に報告しているので、よい図版がないか探してみたことがあります。
アイルランド農村社会の歴史を調べるときに使いました。19世紀半ばにアイルランド大飢饉が起こります。いわゆる「じゃがいも飢饉」です。ILNはこの飢饉を比較的詳細に報告しているので、よい図版がないか探してみたことがあります。
アイルランドのじゃがいも飢饉を描いたILNの有名なスケッチは飢饉の研究でよく使われます
 面白い図版はありましたか。
面白い図版はありましたか。
 アイルランド大飢饉は1845年に始まります。飢饉が最も深刻になるのが1847年です。その時に、ILNはアイルランド出身の画家に、現地からスケッチと解説文を送るように委嘱しています。これらのスケッチは、大飢饉の研究でよく使われます。そのうち特に有名なものに、ぐったりしている赤ちゃんを抱いた母親が物乞いに寄ってくるのを描いた絵があります。今回、トライアルでもう一度見てみたのですが、よく見ると母親は、確かに顔色は悪いのですが、しっかりと立っています。本当に飢えて消耗してしまった人は歩けないはずです。自分の家からも出られず、会話もままならない状態にある人、というのは大飢饉をテーマとした文学作品に描かれています。この女性はその段階には達していない、ということが絵から分かります。ILNの絵はどれも写実的で、大飢饉の悲惨な状況をいたずらに強調するのではなく、眼に見えるものをありのままに描いていたように思います。
アイルランド大飢饉は1845年に始まります。飢饉が最も深刻になるのが1847年です。その時に、ILNはアイルランド出身の画家に、現地からスケッチと解説文を送るように委嘱しています。これらのスケッチは、大飢饉の研究でよく使われます。そのうち特に有名なものに、ぐったりしている赤ちゃんを抱いた母親が物乞いに寄ってくるのを描いた絵があります。今回、トライアルでもう一度見てみたのですが、よく見ると母親は、確かに顔色は悪いのですが、しっかりと立っています。本当に飢えて消耗してしまった人は歩けないはずです。自分の家からも出られず、会話もままならない状態にある人、というのは大飢饉をテーマとした文学作品に描かれています。この女性はその段階には達していない、ということが絵から分かります。ILNの絵はどれも写実的で、大飢饉の悲惨な状況をいたずらに強調するのではなく、眼に見えるものをありのままに描いていたように思います。
とは言え、この絵の赤ん坊はかなり危険な状態にあったはずですし、大飢饉で多くの人命が失われたことも事実です。そこでもう一つ興味をひくスケッチとして、1849年、ヴィクトリア女王が即位後初めてアイルランドを訪問した時の式典などの様子を伝えた絵があります。この時大飢饉はまだ終息していませんが、そのことは沢山ある式典のスケッチ(384-386 号)からは全く伝わってきません。女王は訪問中、大飢饉というアイルランドの負の側面を眼にする機会がなかったということが窺われる絵です。
Her Majesty’s Visit to Ireland August 18, 1849
Sketches in the West of Ireland.– By Mr. James Mahony February 13, 1847
 アイルランド出身の画家にスケッチを書かせたということですが、何という画家ですか。
アイルランド出身の画家にスケッチを書かせたということですが、何という画家ですか。
 James Mahony(Mahoney)と言う人です。アイルランド南部コーク州出身の画家でした。
James Mahony(Mahoney)と言う人です。アイルランド南部コーク州出身の画家でした。
 ILNに収録されたアイルランド関連の絵の中から一枚の絵を挙げるとすれば、どの絵になりますか。
ILNに収録されたアイルランド関連の絵の中から一枚の絵を挙げるとすれば、どの絵になりますか。
 二つの絵を挙げます。一つは、アイルランドの貧農が農地から追放されるのを描いた “Ejectment of Irish Tenantry”(アイルランド小作人の農地追放)という絵です。大飢饉は貧農の主食だったじゃがいもの大凶作が原因です。貧農は生活の糧を失い、公的救貧に依存するようになります。救貧の財源は地方税だったため、地域社会の負担になるとみなされた彼らを、地主は農地から追放してしまいます。この絵は、そのようにして家屋を壊してまで貧農を追放しようとする官憲とそれを嘆き悲しむ人びとを対比して描いたものです。もう一つは、大飢饉中、そして大飢饉が終息した後も、もうこの国では生きていけないと思ったアイルランド人が大量に国外へ移民していくのですが、彼らの出発する前の別れのシーンを描いた “The Depopulation of Ireland”(アイルランドの過疎化)という絵です。
二つの絵を挙げます。一つは、アイルランドの貧農が農地から追放されるのを描いた “Ejectment of Irish Tenantry”(アイルランド小作人の農地追放)という絵です。大飢饉は貧農の主食だったじゃがいもの大凶作が原因です。貧農は生活の糧を失い、公的救貧に依存するようになります。救貧の財源は地方税だったため、地域社会の負担になるとみなされた彼らを、地主は農地から追放してしまいます。この絵は、そのようにして家屋を壊してまで貧農を追放しようとする官憲とそれを嘆き悲しむ人びとを対比して描いたものです。もう一つは、大飢饉中、そして大飢饉が終息した後も、もうこの国では生きていけないと思ったアイルランド人が大量に国外へ移民していくのですが、彼らの出発する前の別れのシーンを描いた “The Depopulation of Ireland”(アイルランドの過疎化)という絵です。
Ejectment of Irish Tenantry December 16, 1848
The Depopulation of Ireland May 10, 1851
描写対象が包括的で正確な描写であることがILNの魅力です
 研究資料としてのILNの魅力はどんなところにありますか。
研究資料としてのILNの魅力はどんなところにありますか。
 描写対象の包括性がまず挙げられます。それから、対象を正確に描いているということです。大飢饉のときにダメになったじゃがいもについても、葉から根まで実に丁寧に描いています。菌類の一種が寄生したことが大飢饉の原因ですが、当時は昆虫が何かを持ち込んでいるのではないかという説も唱えられ、犯人と目された種々の昆虫についても詳細に描かれています。人物については、デッサンがしっかりしているように思えます。芸術性はおそらくゼロでしょうが、確かな技術をもって描かれていることが伺えます。
描写対象の包括性がまず挙げられます。それから、対象を正確に描いているということです。大飢饉のときにダメになったじゃがいもについても、葉から根まで実に丁寧に描いています。菌類の一種が寄生したことが大飢饉の原因ですが、当時は昆虫が何かを持ち込んでいるのではないかという説も唱えられ、犯人と目された種々の昆虫についても詳細に描かれています。人物については、デッサンがしっかりしているように思えます。芸術性はおそらくゼロでしょうが、確かな技術をもって描かれていることが伺えます。
The Potato Murrain August 29, 1846
Re-Appearance of the Aphis Vastator on the Potato Plant June 12, 1847
写実性が高く信頼できることが、ILNの絵がよく使われる理由だと思います
 学術雑誌に掲載される論文のことは分かりませんが、研究者が一般読者向けに書く啓蒙書や教科書の類にはILNの絵がしばしば掲載されるのを眼にします。どうして、他の新聞や雑誌ではなくILNの絵がよく掲載されるのでしょうか。
学術雑誌に掲載される論文のことは分かりませんが、研究者が一般読者向けに書く啓蒙書や教科書の類にはILNの絵がしばしば掲載されるのを眼にします。どうして、他の新聞や雑誌ではなくILNの絵がよく掲載されるのでしょうか。
 難しい質問ですね(笑)。一つ言えるのは、信頼性があるということですね。写実性の高い絵だということは広く認識されていると思います。逆に言うと、デフォルメされていないということです。どの絵も精密ですね。この時代、絵は銅板だったのでしょうか。
難しい質問ですね(笑)。一つ言えるのは、信頼性があるということですね。写実性の高い絵だということは広く認識されていると思います。逆に言うと、デフォルメされていないということです。どの絵も精密ですね。この時代、絵は銅板だったのでしょうか。
 木版ですね。ILNが創刊された頃、木版が復興していたようです。
木版ですね。ILNが創刊された頃、木版が復興していたようです。
 木版であそこまで精密・正確に描かれるというのは、凄いことですね。絵師だけでなく、版画師にも相当に凄腕の人々がいたということでしょう。それからもう一つ、特に人物について、一瞬の動きを捉えるのがうまいという印象を受けます。大飢饉の絵では、嘆いている人々の瞬間の動きがうまく捉えられています。瞬間の感情を伝えるには、文章よりも絵の方がはるかに強力ですからね。
木版であそこまで精密・正確に描かれるというのは、凄いことですね。絵師だけでなく、版画師にも相当に凄腕の人々がいたということでしょう。それからもう一つ、特に人物について、一瞬の動きを捉えるのがうまいという印象を受けます。大飢饉の絵では、嘆いている人々の瞬間の動きがうまく捉えられています。瞬間の感情を伝えるには、文章よりも絵の方がはるかに強力ですからね。
 学術雑誌の論文ではILNはこれまでどのような扱いを受けているのですか。よく引用されるのでしょうか。
学術雑誌の論文ではILNはこれまでどのような扱いを受けているのですか。よく引用されるのでしょうか。
 私の専門分野に限って言えば、引用されることはほとんどありません。そもそも、学術雑誌に絵が載ることはまずありませんから。本でしたら、信頼できる史料として使われているように思います。
私の専門分野に限って言えば、引用されることはほとんどありません。そもそも、学術雑誌に絵が載ることはまずありませんから。本でしたら、信頼できる史料として使われているように思います。
ILNのようなデータベースの登場で、美術史家と歴史家の垣根が取り払われるかもしれません
 歴史研究で使う資料の大半は文字資料です。ILNのようなイメージ資料がデータベース化されたことは歴史研究にとってどのような意義がありますか。
歴史研究で使う資料の大半は文字資料です。ILNのようなイメージ資料がデータベース化されたことは歴史研究にとってどのような意義がありますか。
 美術史家は図像分析を行ないますが、それ以外の歴史家はほとんど文字史料のみを使ってきました。図像分析には図像分析の作法があります。美術史家と歴史家の間で一種の棲み分けがなされてきたのだと思います。ILNのようなデータベースの登場で、その垣根が取り払われるかも知れません。
美術史家は図像分析を行ないますが、それ以外の歴史家はほとんど文字史料のみを使ってきました。図像分析には図像分析の作法があります。美術史家と歴史家の間で一種の棲み分けがなされてきたのだと思います。ILNのようなデータベースの登場で、その垣根が取り払われるかも知れません。
一次史料も使う歴史教育を進めるとき、ILNのような図版入りのデータベースは大きな意味を持ちます
 テキスト中心の資料と異なり、ILNは歴史の教育にも充分に活用できると思います。授業でお使いになるとすれば、どのように使ってみたいとお考えですか。
テキスト中心の資料と異なり、ILNは歴史の教育にも充分に活用できると思います。授業でお使いになるとすれば、どのように使ってみたいとお考えですか。
 重要なポイントです。大学での歴史教育は二次文献・研究文献に書かれたことを伝えるのが主なスタイルになっています。学生が自分で一次史料を探してきて、それを解釈するという経験は、卒論を書くまでほとんどないのが現状です。二次文献中心の歴史教育を一次史料も使う歴史教育に変えるときに、データベース、特にILNのような図版の入ったデータベースは大きな意味を持ちます。学生に宿題を与えて、データベースを使って調査させるということもできると思います。
重要なポイントです。大学での歴史教育は二次文献・研究文献に書かれたことを伝えるのが主なスタイルになっています。学生が自分で一次史料を探してきて、それを解釈するという経験は、卒論を書くまでほとんどないのが現状です。二次文献中心の歴史教育を一次史料も使う歴史教育に変えるときに、データベース、特にILNのような図版の入ったデータベースは大きな意味を持ちます。学生に宿題を与えて、データベースを使って調査させるということもできると思います。
 留学や在外研究でイギリスに滞在された経験をお持ちだと思いますが、外国のデータベースの利用状況は日本と比較してどのようにご覧になっていますか。
留学や在外研究でイギリスに滞在された経験をお持ちだと思いますが、外国のデータベースの利用状況は日本と比較してどのようにご覧になっていますか。
 私の専門分野で言えば、イギリスやアイルランドの方が関連資料が揃っているのは当然としても、データベースの利用状況という点では、日本はそれほど引けを取っていないと見ています。
私の専門分野で言えば、イギリスやアイルランドの方が関連資料が揃っているのは当然としても、データベースの利用状況という点では、日本はそれほど引けを取っていないと見ています。
アイルランドに対する眼差しを見ると、『パンチ』が辛辣であるのに対して、ILNには温かさを感じます
 19世紀の挿絵入り定期刊行物にはILNの他に『パンチ』があり、これも小社が創刊号からデータベースでご提供していますが、アイルランドに対する『パンチ』とILNの眼差しの違いを感じますか。
19世紀の挿絵入り定期刊行物にはILNの他に『パンチ』があり、これも小社が創刊号からデータベースでご提供していますが、アイルランドに対する『パンチ』とILNの眼差しの違いを感じますか。
 端的に言って、パンチは辛辣ですね。アイルランド人はフランケンシュタインになぞらえられたりするなど、悲惨な描かれ方をすることがあります。それは、たとえ大飢饉中であっても、ILNではあり得ないことです。ILNのアイルランドに対する眼差しは温かいと思います。『タイムズ』も『パンチ』と同じように、アイルランドに対して辛辣ですね。
端的に言って、パンチは辛辣ですね。アイルランド人はフランケンシュタインになぞらえられたりするなど、悲惨な描かれ方をすることがあります。それは、たとえ大飢饉中であっても、ILNではあり得ないことです。ILNのアイルランドに対する眼差しは温かいと思います。『タイムズ』も『パンチ』と同じように、アイルランドに対して辛辣ですね。
《関連エッセイ:世相を映す合わせ鏡:『パンチ』と『タイムズ』》
November 4, 1843, Punch
May 20, 1882, Punch
 ILNのアイルランドに対する温かい眼差しは、文章からも図版からもお感じになりますか。
ILNのアイルランドに対する温かい眼差しは、文章からも図版からもお感じになりますか。
 両方からそう感じます。ILNに収録されているアイルランド関連の図版は特別に多いわけではありませんが、私が見た限りでは、意地悪な絵は見つかりませんでした。『パンチ』の図版を史料として使う場合は、なぜこうも辛辣だったのかという前提から説明しなければなりませんが、ILNはそのまま使えます。もちろん、先に言った図像分析の作法に則してのことですが。
両方からそう感じます。ILNに収録されているアイルランド関連の図版は特別に多いわけではありませんが、私が見た限りでは、意地悪な絵は見つかりませんでした。『パンチ』の図版を史料として使う場合は、なぜこうも辛辣だったのかという前提から説明しなければなりませんが、ILNはそのまま使えます。もちろん、先に言った図像分析の作法に則してのことですが。
『タイムズ』がアイルランドに対して辛辣だったのは、自己責任論の立場に立っていたからです
 『パンチ』がアイルランドに対して意地悪だったというのは、諷刺画としての性格から納得がゆきますが、『タイムズ』が意地悪だったというのは、どのような背景があるのでしょうか。
『パンチ』がアイルランドに対して意地悪だったというのは、諷刺画としての性格から納得がゆきますが、『タイムズ』が意地悪だったというのは、どのような背景があるのでしょうか。
 『タイムズ』は、社会問題に関して基本的に自己責任論の立場に立っていました。当時アイルランドは連合王国の一部だったのにもかかわらず、アイルランドの貧困は、アイルランドの人々が怠けているから悪いのだ、というのがタイムズの基本的な発想法です。アイルランド人は生来、法と勤勉に馴染まない性質をもっているのではないかという、人種主義的な言い方さえすることがありました。また、アイルランドの貧民だけでなく、自治を求めるナショナリストに対しても敵対的でした。
『タイムズ』は、社会問題に関して基本的に自己責任論の立場に立っていました。当時アイルランドは連合王国の一部だったのにもかかわらず、アイルランドの貧困は、アイルランドの人々が怠けているから悪いのだ、というのがタイムズの基本的な発想法です。アイルランド人は生来、法と勤勉に馴染まない性質をもっているのではないかという、人種主義的な言い方さえすることがありました。また、アイルランドの貧民だけでなく、自治を求めるナショナリストに対しても敵対的でした。
アイルランド主席政務官殺害にアイルランドのナショナリスト、チャールズ・パーネルが関与したことを記した手紙を掲載したタイムズの記事。後にこの手紙は偽造であることが判明し、『タイムズ』は裁判で敗訴する。
Parnellism and Crime April 18, 1887, The Times
ILNは女王の豪華な式典のスケッチを掲載しつつ、アイルランド救済を呼びかける投書も掲載しています
 ILNは、数ある新聞の中でも中立的な立場で論じている、という捉え方をすることができますか。
ILNは、数ある新聞の中でも中立的な立場で論じている、という捉え方をすることができますか。
 そこが重要なポイントです。目に映ったものをそのまま描いているように見えますが、アイルランドの惨状を写実的、もしくは写実的に見える形で描くということが、当時は政治的メッセージになり得たのです。例えば、大飢饉中に、ヴィクトリア女王訪問時の豪勢な式典のスケッチを掲載する一方で、同じ号(384号)に、「イングランドは大飢饉に苦しむアイルランドを救う義務がある」と呼びかける匿名のイングランド人からの投書も載せています。二つをあわせれば、アイルランドがこんなに苦しんでいるのに政府や国王は何をしているのか、との思いを読者に抱かせることになりかねません。にもかかわらず、二つをそのまま掲載したのは、ILNがアイルランド寄りであることを示していると私は思います。
そこが重要なポイントです。目に映ったものをそのまま描いているように見えますが、アイルランドの惨状を写実的、もしくは写実的に見える形で描くということが、当時は政治的メッセージになり得たのです。例えば、大飢饉中に、ヴィクトリア女王訪問時の豪勢な式典のスケッチを掲載する一方で、同じ号(384号)に、「イングランドは大飢饉に苦しむアイルランドを救う義務がある」と呼びかける匿名のイングランド人からの投書も載せています。二つをあわせれば、アイルランドがこんなに苦しんでいるのに政府や国王は何をしているのか、との思いを読者に抱かせることになりかねません。にもかかわらず、二つをそのまま掲載したのは、ILNがアイルランド寄りであることを示していると私は思います。
State of Ireland August 11, 1849
 今おっしゃった、『タイムズ』の自己責任論は、以前インタビューさせていただいた専修大学の永島剛先生が、コレラが流行したときに、『タイムズ』が政府の介入を批判する論説を掲載したことを指摘されていました。タイムズのコレラに対するスタンスとアイルランドに対するスタンスは一貫していたということでしょうか。
今おっしゃった、『タイムズ』の自己責任論は、以前インタビューさせていただいた専修大学の永島剛先生が、コレラが流行したときに、『タイムズ』が政府の介入を批判する論説を掲載したことを指摘されていました。タイムズのコレラに対するスタンスとアイルランドに対するスタンスは一貫していたということでしょうか。
 そうだったのですか。なるほど、勉強になりました。ところで、イングランドの貧民に対しても、アイルランドの貧民に対しても、『タイムズ』が同じような冷たい眼差しを注いでいたとしたら、首尾一貫していたということができます。でも、そうとは言い切れないところもあります。アイルランドにはアイルランド特有の問題があり、イングランドの貧民よりもアイルランドの貧民の方が始末が悪い、と『タイムズ』は思い込んでいた節があります。
そうだったのですか。なるほど、勉強になりました。ところで、イングランドの貧民に対しても、アイルランドの貧民に対しても、『タイムズ』が同じような冷たい眼差しを注いでいたとしたら、首尾一貫していたということができます。でも、そうとは言い切れないところもあります。アイルランドにはアイルランド特有の問題があり、イングランドの貧民よりもアイルランドの貧民の方が始末が悪い、と『タイムズ』は思い込んでいた節があります。
『タイムズ』の議会速記録は、ハンサードの情報源であり、ハンサード以上に現場の雰囲気を良く伝えていた可能性は否定できません
 先生のご研究分野の中で、ILN以外に関心をお持ちの新聞はありますか。
先生のご研究分野の中で、ILN以外に関心をお持ちの新聞はありますか。
 やはり、まずタイムズを挙げなければなりません。19世紀の国会議員の発言を調べる場合、最も「生の声」に近い史料が『タイムズ』です。議会の討論というと、ハンサードという本の形になったものが史料として使われることが多いのですが、19世紀を通じて、ハンサードより『タイムズ』の方が正確だったと言われています。
やはり、まずタイムズを挙げなければなりません。19世紀の国会議員の発言を調べる場合、最も「生の声」に近い史料が『タイムズ』です。議会の討論というと、ハンサードという本の形になったものが史料として使われることが多いのですが、19世紀を通じて、ハンサードより『タイムズ』の方が正確だったと言われています。
 ハンサードより『タイムズ』の方が正確なのですか!それは驚きました。
ハンサードより『タイムズ』の方が正確なのですか!それは驚きました。
 「正確」と言うのはやや「不正確」だったかも知れません。実はハンサードの情報源は、『タイムズ』を始めとするロンドンの新聞でした。『タイムズ』は専門の速記者を派遣して議員の発言を記録させ、それを翌日紙面で報道しています。ハンサードは基本的に自前の記者を持たなかったので、そうした新聞報道を手際よく編集し、しばしば議員本人にそれを手直しさせた上で、数年後に公刊する形をとっていました。速記者がどこまで議員の発言に忠実だったのかと言う問題は残りますが、『タイムズ』の方が現場の雰囲気を良く伝えていた可能性は否定できません。また情報量も『タイムズ』の方が多くなります。
「正確」と言うのはやや「不正確」だったかも知れません。実はハンサードの情報源は、『タイムズ』を始めとするロンドンの新聞でした。『タイムズ』は専門の速記者を派遣して議員の発言を記録させ、それを翌日紙面で報道しています。ハンサードは基本的に自前の記者を持たなかったので、そうした新聞報道を手際よく編集し、しばしば議員本人にそれを手直しさせた上で、数年後に公刊する形をとっていました。速記者がどこまで議員の発言に忠実だったのかと言う問題は残りますが、『タイムズ』の方が現場の雰囲気を良く伝えていた可能性は否定できません。また情報量も『タイムズ』の方が多くなります。
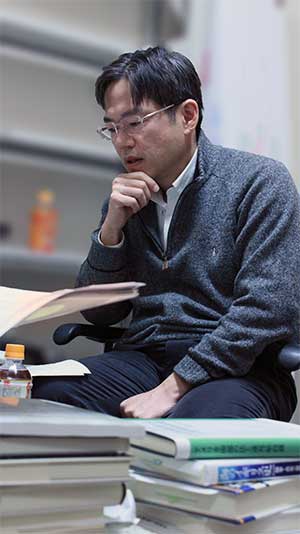
『タイムズ』の他では、『マンチェスター・ガーディアン』が読んでいて面白いですね。マンチェスターはアイルランド人移民が多いため、『マンチェスター・ガーディアン』は『タイムズ』よりアイルランド人に同情的になります。新聞の相違と言えば、論調の相違だけではありません。デザイン、字体にも各紙の個性が出ます。シャーロック・ホームズの『バスカヴィル家の犬』で、新聞の切抜きを見ただけでホームズが「これは『タイムズ』の論説だ」と、見抜く場面があります。フィクションの世界の話だろうと思っていましたが、私の知り合いのアイルランド人の先生は、『ガーディアン』で同じようなことをやりました(笑)。
ILNのデータベースは、インタフェースが利用者に対して親切な設計になっていると感じました
 このデータベースの機能について、どのような感想をお持ちになりましたか。
このデータベースの機能について、どのような感想をお持ちになりましたか。
 データベースとしては大変使いやすいものでした。検索結果一つずつにチェックボックスがついてくるなど、親切な設計になっていると感じました。閲覧範囲を一つの記事だけ、またはページ全体、というように選択できるのも、使いやすいと思いました。それと、図版をダウンロードするとき、データ容量が重いため、どうしても多少の時間がかかりますが、許容範囲だと思いました。
データベースとしては大変使いやすいものでした。検索結果一つずつにチェックボックスがついてくるなど、親切な設計になっていると感じました。閲覧範囲を一つの記事だけ、またはページ全体、というように選択できるのも、使いやすいと思いました。それと、図版をダウンロードするとき、データ容量が重いため、どうしても多少の時間がかかりますが、許容範囲だと思いました。
 それ以外に、こういう機能があればよいというご注文があれば、お聞かせください。
それ以外に、こういう機能があればよいというご注文があれば、お聞かせください。
 たとえば、”Ireland”, “Potato” で検索すると検索結果が出てきますが、各々の検索結果がテキスト情報なのか、イメージ情報なのか、識別することはできますか。
たとえば、”Ireland”, “Potato” で検索すると検索結果が出てきますが、各々の検索結果がテキスト情報なのか、イメージ情報なのか、識別することはできますか。
 はい、各々の検索結果について、その検索結果にイメージ情報が含まれている場合は、カメラのアイコンが表示されます。それから、詳細検索画面では検索条件をイメージ情報だけに絞り込む方法もあります。この場合は、イメージ情報のない記事が検索対象から外れます。さらに、イメージ情報のキャプションを検索範囲に指定して検索するという機能もあります。
はい、各々の検索結果について、その検索結果にイメージ情報が含まれている場合は、カメラのアイコンが表示されます。それから、詳細検索画面では検索条件をイメージ情報だけに絞り込む方法もあります。この場合は、イメージ情報のない記事が検索対象から外れます。さらに、イメージ情報のキャプションを検索範囲に指定して検索するという機能もあります。
今日は、勝田先生の研究領域であるアイルランドをテーマにILN、パンチ、タイムズについてお話いただきました。その中で、アイルランドに対する眼差しの相違という興味深い論点が引きだされました。また、議会の討論の記録としては、タイムズ等の新聞記事が、あのハンサードの情報源だったという、極めて重要なご指摘もいただきました。大変有益なインタビューでした。勝田先生、どうもありがとうございました。
※このインタビューを行なうに際して、紀伊國屋書店様のご協力をいただきました。ここに記して感謝いたします。
ゲストのプロフィール
勝田俊輔先生 (かつた・しゅんすけ)
学歴:
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程西洋史学専攻 単位取得退学
主な著書:
主な論文:
現在(2021年)東京大学大学院人文社会系研究科教授